城壘12
丸MARU 1989年12月号 通算521号 連載第12回
中国兵はどこへ消えたり?
 都城連隊の鎌田上等兵はほとんど眠ることもなく城壁上で十三日の朝を迎えた。寒かったけれど、緊張で眠気も空腹も感じない。城壁は占領したものの、城内の中国軍との戦いがひかえており、夜が明けると、他の中隊も破壊ロから登ってきた。新しく登ってきた兵隊は、揃うとそこから城内に下りて、町の中心に向かって進んでいった。
都城連隊の鎌田上等兵はほとんど眠ることもなく城壁上で十三日の朝を迎えた。寒かったけれど、緊張で眠気も空腹も感じない。城壁は占領したものの、城内の中国軍との戦いがひかえており、夜が明けると、他の中隊も破壊ロから登ってきた。新しく登ってきた兵隊は、揃うとそこから城内に下りて、町の中心に向かって進んでいった。
鎌田上等兵たちは彼らを見ながらそのまま城壁上で守りにつき、しばらくしてから城壁上を西に進むことになった。
進んでいく途中、城壁上には昨夜の夜襲でたおれた中国兵が何人も死んでいるのに出会った。しかし中国軍からの攻撃はどこからもなく、そのまま一キロほど城壁上を進み、水西門まで行ったところで、城内に下りた。
水西門は楼門の造りで、門は三重からなる立派なものであった。水西門から入った城内は水西門大街という繁華街になっており、繁華街の通りには土嚢が積み上げられ、陣地が築いてある。しかし、土嚢から撃ってくる様子はなく、中国兵は一人も見当たらない。建物のいくつかは昨日の日本軍の砲撃で壊れていて、一人の市民もみあたらない。
繁華街を注意深く進み、水西門一帯に中国軍がいないとわかると、鎌田上等兵たちは中国軍の砲撃の拠点であった清涼山に向かうことになった。弘法大師が修行したという有名な山である。
清涼山は南京城壁よりやや高いくらいの小高い丘で、六門の重砲があった。
ここにも中国軍はいなかった。夜半まであれほど激しく砲撃し、何度も夜襲を繰り返していた中国兵は一体どこに逃げていったのだろうか。わずか数時間の間で中国軍はかき消すように消えていた。
鎌田上等兵たちの城内掃討地区は水西門近くの一画だったので、清涼山まで行くとそこまでにして、しばらくしてから水西門まで戻ることになった。
結局、鎌田上等兵は城内で一人の中国兵も見ることなく、この日は水西門近くの民家に宿営した。
一方、中山門外の西山の陣地で寝ていた山室伍長たちは、十三日のまだ暗い午前六時、突然、命令を受け取った。中国軍は退却した模様なのでただちに追撃せよ、との命令である。わずか数時間前までは中国軍と激しく撃ちあっていただけに、中国軍が退却したらしいという話にはすぐさま信用できず、山室伍長は驚いた。ともあれ山室分隊は頂上付近の塹壕にいたので、追撃の準備をして急いで丘を下りた。
下りると、そこは中山門に通じるアスファルトの中山公路である。西山にいた他の重機関銃隊にも同じ命令が届いたらしく、つぎつぎに西山から下りてきた。重機関銃中隊は中山公路上で一緒になると揃って中山門に向かうことになった。もう夜が明けようとしている。
昨夜、午前零時を過ぎるころ、福知山連隊の中で予備隊として後方を進んでいた第二大隊の将校斥候が中山門に向かった。暗闇を利用して中山門に向かうと、近付くにしたがって中国軍の守備が手薄になっていく。中山門にたどりつくと、一帯は静かで、中山門の守りについた中国軍は撤退している様子であった。斥候はただちに引き返して第二大隊本部に報告し、報告を受けた第二大隊では西山にいる第一線部隊を追い越して中山門まで進んだ。
中山門に進んでみると、中国軍からの攻撃はなく、中国軍は中山門から完全に撤退していたことがわかった。
結局、中山門の最後の攻防戦は福知山連隊のだれもが意識しないまま十二日で終わっていたのである。
第二大隊が到達した中山門は三つのアーチが並んでいて、どれも厚い鉄の扉で閉じてあり、内側には土嚢がうず高く積み重ねてある。そのため門からは入れなかったけれど、三日間にわたる野砲による砲撃で中山門脇の城壁が崩れ、瓦礫で急な坂道ができていた。
第二大隊はここから中山門に登り、このとき城門の扉に「大野部隊占領 十二月十三日午前三時十分」と記した。
中山門占領の知らせは連隊本部に届けられ、大野連隊長は病気で日本に返っていたので連隊長代理の青木少佐以下が六時過ぎ中山門に登った。
山室分隊たちに直ちに追撃せよとの命令がきたのはそのころである。
結果として中山門占領に遅れてしまうことになった山室分隊たちが中山門に向かって進むと、中山公路の道路脇にあるプラタナスの並木はことごとく切られ、道路に押し倒されていた。道路のまわりにある竹林の竹も根本から切られ、切り口は矢のように尖っている。中国軍は日本軍の進撃をくいとめようと考えられる限りの防御を施していたのだ。
そういう光景を見ながら中山門までくると、中山門上には日章旗がはためいていた。
中山門外までくると山室分隊たちは、城壁の外でしばらく待機させられた。
しばらく待機して、午前一時半、これから城内掃討を行うという命令が下った。山室分隊たちは中山門脇の瓦礫の坂を登った。
中山門の上にはトーチカがあり、あちらこちらに砲撃でたおれた中国兵の死体があった。トーチカには重機関銃の銃眼があり、ドイツ軍の指揮で一年は持ちこたえられるようにしてあるという噂がまんざらでもないと山室伍長は思った。
山室分隊たちは中山門の上まで登ると大声で万歳三唱をし、すぐに瓦礫を下りた。
城内に入ると、中山門からは幅十数メートルの立派なコンクリート道路が真っすぐに伸びている。約ニキロメートルにわたって伸びているこの道路は中山東路といい、数年前に作られたものである。山室分隊はこの中山東路の両側を二手に分かれて進むことになった。
軍服を脱いで市民に変装
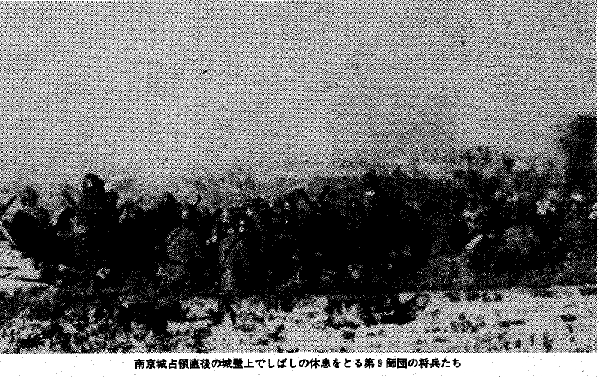 中山門から数百メートル進むと、明の故宮がある。南京城が建てられたのは明の太祖朱元璋がここを首都と定めた五百七十年ほど前で、そのとき、この地に宮殿が建てられた。即ち紫禁城で、八百メートル四方の豪華な宮殿である。しかし、その後、明の首都は北京に変わった上、清、中華民国と変わり、今はわずかに石の柱が残っているだけで、それだけから宮殿は想像もできなかった。あたり一面は野原で荒涼としている。しかも遺跡は中山東路で二つに分断されていた。
中山門から数百メートル進むと、明の故宮がある。南京城が建てられたのは明の太祖朱元璋がここを首都と定めた五百七十年ほど前で、そのとき、この地に宮殿が建てられた。即ち紫禁城で、八百メートル四方の豪華な宮殿である。しかし、その後、明の首都は北京に変わった上、清、中華民国と変わり、今はわずかに石の柱が残っているだけで、それだけから宮殿は想像もできなかった。あたり一面は野原で荒涼としている。しかも遺跡は中山東路で二つに分断されていた。
故宮から進むと左手に飛行場があり、右手にはポツンポツンと建物が建ち始める。建物はほとんどが軍の建物で、蒋介石の住まいがある励志社もある。
中山東路を進んで行くうちに、数機の飛行機が上空高く飛んできた。制空権は完全に日本が握っていたので、山室伍長がのんびり見上げると、やがて飛行機は日本兵を狙うように真上まで来て、突然、爆弾を投下した。爆弾は近くで爆発して、兵隊たちはくもの子をちらすように逃げだした。
飛び去っていく飛行機をよく見るとやはり日本機である。日本機は、まだ日本軍が城内まで進出しておらず、中国兵だと思って爆撃したらしい。戦闘の最先端ては仕方ないことだが、もし友軍の爆撃で命を落とすのではいくら死を覚悟しているといってもあきらめきれないと日本機を見ながら思った。
幸いなことに負傷者はだれもいなかった。
さらに進むと、中山東路を横切って流れるクリークがあり、近くにはトーチカがいくつもあった。中国軍は中山門が落とされてもさらに城内のこの辺りで戦おうとしてトーチカを作ったものらしい。城外のプラタナスの伐採といい、城内のトーチカといい、幾重にも防御がはどこされているのにはただ感嘆するだけである。
しかし、トーチカの回りには一人の中国兵も見当たらない。山室分隊はじめこのとき城内を進んでいる部隊は中国軍に撤退命令が出ているなどとは夢にも思っていない。緊迫してくる。
城内のクリークを超えるころから道路の両脇に建物が建ち並びはじめた。いよいよ中心街にさしかかり、山室分隊は慎重に進んだ。完全を期すためには建物一つ一つを掃討しなくてはいけないが、迅速に進まなければならなかったから通りに面した大きい建物だけを調べて進んだ。
進むにつれて、道路にチェコ銃が投げ捨てられたり、軍服が脱ぎ捨てられているのに出会いだした。中国兵は市民に変装して建物に隠れているのかもしれない。さらに緊張した。
そのうち予想した通り軍服を脱いで市民を装っていた中国兵が何人かすつ建物に隠れているのを発見した。発見と同時に福知山連隊は一斉に撃った。一瞬でも遅れたほうがやられてしまう。
中国兵をたおすと、そのままに進む。
中山門から入って二時間ほどたったころ、道路かロータリーになっている所にぶつかった。福知山連隊の担当掃討区域は、中山門とロータリーを結ぶ線から北側一帯である、そこで山室分隊はロータリーから右に折れて、同じようにコンクリート舗装の道路を進んだ。中山路である。中山路を進むと、急にざわざわと人の気配がしてきた。やがて通りの左側にある建物に黒山のように人々が群がっているのが見え出した。近付くと女や子供だけで、男はほとんどいない。彼らは避難した市民らしく、ホッとしたようすで福知山連隊を見ている。中には喜んで手を振っている人もいる。一帯には赤く卍の形を染め抜いた長い布が張ってあり、この布の張られた区域が避難区域であるらしかった。
しかしこの中にも中国兵は隠れているのではなかろうか。便衣に変装している中国軍と撃ち合った直後だけに、彼らを見た福知山連隊の兵隊たちはそう思った。
十二月に入り南京市長の馬超俊が南京を離れ、役人たちもつぎつぎ去っていったが、このとき、南京城内には二十数人の第三国人が残っていた。布教活動を行っていたアメリカ宣教師やアメリカのミッション系大学で教えていた大学教授、さらに南京で商売をしていたドイツやイギリスの商人たちである。彼らは第三国人ということで日中両国から身分を保障されていたためドイツ人のラーベを委員長に難民区国際委員会を作り、南京に残った市民を助けようとした。難民区国際委貝会は城内に国際難民区を設け、ここで食糧などを与えようとし、中国政府と日本政府に難民区を認めるよう要請した。
この申し出に対して、中国側は市政府関係者がほとんど避難していたので渡りに船と認めた。しかし、日本側は、南京城内はやがて戦闘地域になるだろうと予想しており、難民区を設けるといっても戦闘地域とはっきり区別できる目印もないし、また、国際委員会は実力が伴わないので、中国兵が難民区に隠れようとした場合、阻止できないだろうとの理由で認めなかった。
それでも難民区国際委員会は難民区を設けたので、日本軍は隷下部隊に命令して難民区を砲撃しないようにした。
南京に残った市民の多くは食糧と身の安全を求めて難民区に集まった。この地域にはアメリカ人所有の大学や中学校があったので市民が集まるのには便利であった。難民区に集まった市民の数は十二万ともいわれたから、南京に残った市民の八割ほどがここに集まったことになる。
市民は生活に必要なものだけを持って集まったが、狭い地域だけに雑踏、喧噪をきわめていた。それでも中国人は戦乱なれしていることもあり、難民区内にはすぐに難民相手の店が現れたり、大道芸人が芸を始め、若い湯女がマッサージする支那風呂も開かれた。この難民区で実際手足となって働いたのは慈善団体である紅印字会の人々で、山室分隊が見た卍を染め抜いた布は紅卍字会の印であった。
光華門を占領した鯖江連隊
 しかし、難民区では日本軍が恐れていることがおきていた。
しかし、難民区では日本軍が恐れていることがおきていた。
昨夜、撤退命令が出たとき、城内の中国軍は、光華門や中華門と反対の揚子江側にある挹江門や興中門に向かった。しかし既に各門は防衛のため内側に土嚢を積んで開かないようにしてあったため、いざ逃げようとしても大軍が逃げることはできなかった。一つの方法として、城壁の上から縄や布をたらしてこれを伝わって逃げようと考えられた。しかし逃げまどう多数の中国兵がわずかな縄や布に一斉に飛び付いたため、混乱が起き、滑って城壁の下に墜落し、その上に別の中国兵が殺到して下敷きになって圧死する者が相次いだ。城壁を超えて撤退した兵隊はいたけれど、しかしそれは一部で、多くは逃げ切れなかった。
逃げ切れなかった中国兵は市街地に戻り、軍服を脱ぎ捨て、市民に変装して難民区に入り込んだ。難民区の前の中山路や中山北路に脱ぎ捨てられた軍服は何百、何千という数に達した。軍服だけでない。軍帽、脚絆、銃、手榴弾なども捨てられた。
難民区国際委員会は、中国兵が便衣に着替えて難民区に入り込もうとすると、日本側が反対した理由を知っていながら中国兵を積極的に受け入れた。これは完全に日本に対する敵対行為である。
しかし、難民区国際委員会の後ろにはアメリカ、イギリス、ドイツ政府が控え。しかも難民区の建物の多くはアメリカの建物である。日本軍は敵対行為だからといって簡単に難民区国際委貝会を非難するわけにはいかなかった。
難民区域は金沢の連隊の担当だったので、山室分隊はこれらの建物に入らず、中山路を挟んで反対の地域の掃討を続けた。
中山路を進み、やがて左折すると中山北路になる。中山北路に進むと、大きい建物に中国軍がたてこもっていた。城外に逃げ切れないと判断した中国軍の一部がまとまってたてこもったのである。
中山北路の建物にはこういった中国軍のグループがいくつかあり、福知山連隊も近くの建物を利用して本格的に攻撃した。
まもなく日が暮れ、そのため山室分隊は途中で掃討を切り上げることになった。最前線から戻った三階建ての庚姦祥百貨店に宿営することにした。
百貨店内に入ってみると、貴重なものや高価なものは何もなかったが、下着、タオルなど日用雑貨が残っており、それらは兵隊にとって宝石などよりも貴重々ものてあった。半月以上も風呂に入っていなかったから下着は汚れほうだいである。兵隊たちは大騒ぎして思い思いのものを身につけた。
光華門は十三日朝、鯖江連隊が占領したけれど、この門からは鯖江連隊の他に同じ師団の敦賀連隊も入ることになった。
西坂上等兵たち第六中隊はしばらく城壁上にとどまったのち、掃討のために城内に入っていった。光華門のまわりは殆ど建物はなかったけれど、城壁に沿って光華門の西側にある通済門方面に進むと市街地になる。しかし辺りは静かで、市街地を進みながらその静けさは昨日までと比べるとあまりにも対照的なので落ち着かなかった。住民は一人も見掛けることなく、中国兵もいない。家はどこも空き家で、多くの家は既に略奪されてめぼしいものは殆ど残っていないようであった。
西坂上等兵たちは光華門から一キロメートルほど進み、城内を南北に走る鉄道線路の手前まで行つた。その先は第百十四師団の掃討地域である。 結局、この地域では何もなく二時間ほどで戻ってきた。
南京城内での第一夜であったその日、西坂上等兵たち第六中隊は線路近くの申家港の壊れた建物に宿営することになった。
はじまった中国兵の処刑
南京城を南から攻めた宇都宮の第六十六連隊は十三日朝、城壁の外で中国軍と対峙しながら中華門から城内に突入しようとしていた。中華門は第六師団の中でも遅れていた熊本の連隊が前夜遅く、正確には十三日午前一時過ぎに占領していた。しかし、東から中華門に向かった水戸と宇都宮の連隊はその前にいる中国軍を攻め切れず、先頭の水戸連隊は多くの犠牲を出していた。閉ざされた中華門の前で戦っていた中国兵は、逃げ道がなく、しかも彼らには撤退命令が届いていなかったため、水戸や宇都宮連隊相手に死に物狂いで戦っていた。
それでも中国軍には補給される弾薬、食糧もなく、まとまって戦い続けることはできなくなり、次第に数人単位になっていった。
日本軍が中華門からやや東によった城壁に砲撃を行うと、城内や城壁上の中国軍側から反撃はなかった。水戸や宇都宮の先頭の兵隊たちは十時過ぎ中華門の東よりの城壁から登った。そしてそのまま城内に入っていった。
第百十四師団では高崎と松本の部隊が前日の夕方、中華門からさらに東よりの雨花門を占領したため、この日師団司令部は雨花門前方に進むことになっていた。宇都宮連隊のうち第二大隊は師団司令部の護衛をしており、師団司令部とともに雨花門方面に移った。十時過ぎに中華門よりの城壁を占領すると、宇都宮の連隊本部も城壁上に進み、第三大隊は連隊本部とともに城壁上から城内に入っていた。このとき、連隊旗護衛中隊である第一大隊の中の第二中隊も連隊長とともに城内に入った。
残る第一大隊でも第一、第三、第四中隊のうち、第一、第三中隊の一部も城内に入っていたため第四中隊を中心とした兵隊だけが中華門前で抵抗している中国兵と戦っていた。第四中隊も早く城壁前にいる敵を殲滅して城内に入らなければならなかったが、昨日とらえた中国兵の管理もしなければならなかったので作戦は進まなかった。
昨日から中国兵の管理をしていた高松伍長は、十三日の朝を迎えると、いったい自分たちも満足に食べていないのに、この中国兵にどうやって食べさすのだろうかと思った。
まもなく、中国兵管理のため第四中隊の作戦が進まないので、中国兵を百名位ずつ第一中隊と第三中隊に分けるようにとの命令が高松分隊たちにきた。
とはいってもだれが第一中隊と第三中隊を指揮しているのか、また、指揮官がどこにいるのか分からず、命令が出されたとはいえ、すんなり実行されるような状況ではなかった。
それでも兵隊が連絡に走りまわり、とりあえず、第四中隊が管理していた中国兵の一部を第一中隊と第三中隊に分け、分けた方も分けられた方も中国兵を管理しながら中華門まで進むことになった。
各中隊に分けてみたけれど、第四中隊では中国兵の管理に手をとられて作戦が進まないのは変わりなかった。
午後になり、突然、高柳第二小隊長代理が、「中国兵を処刑する」といった。 これ以上中国兵をかかえていても戦闘のさまたげになると考えたらしく、それを聞いて高松伍長
は、中国兵に食べさせるものもないのでそれより方法はないと思った。やるかやられるかの戦闘中だし、彼らを釈放すれば昨夜からの行動から見て日本軍を後方から攻撃するのははっきりしていた。
高柳小隊長代理は処刑命令をすると、自ら持っていた軍刀を抜いて中国兵に斬りつけた。
中国兵は日本軍側に逃げてきた後、素直に従ったり、あるいは、反抗したりしたけれど、多くは逃げたときから観念していたらしく、高柳小隊長代理が斬りつけるのを見てもおとなしくしていた。
その場に居合わせた第四中隊の兵隊は五十人ほどである。兵隊と捕虜の数の割合は一対二ほどなので、高柳小隊長代理が斬りつけるのを見ると、居合わせた兵隊も同じように一人か二人の中国兵に斬りつけた。斬るといっても、中国兵のほとんどは冬服を着ていたので斬殺することも刺殺することもむずかしい。高松伍長は、高柳小隊長代理が斬りつけるのを見て、刺殺することが一番だと思い、中国兵の後ろから後頭部に銃剣を刺した。
一撃で中国兵は絶命した。
銃剣は中国兵の後頭部から深く入ったので、引くとそのま死体が持ち上がった。そうやって二人の中国兵を刺殺したが、この方法が中国兵のためなのだと思った。
だれかが、「戦友が死んだのはこいつらのせいだ」 と叫んだ。中国兵に斬りつけながら、そのとき、だれもがこれで戦友の仇を取ったと思った。終わった後、円匙で土をかけた。
他の中隊もそれぞれ中国兵を殺したけれど、第一中隊は時間がないので、小屋に中国兵を入れたまま灯油をかけて殺そうとしたため、巻脚絆のとれた中国兵が逃げたと後で聞いた。
中国兵の管理はなくなったが、まわりにはまだ中国兵がいて撃ってくる。高松伍長たちは中国兵との戦いを続け、ようやく夕方になって終わった。
翌十四日、高松分隊は城内掃討のため中華門から城内に入った。入るとき、城壁とクリークの間数十メートルの道路には隙間なく中国兵の死体があるのが見えた。城内に戻ろうとした中国兵であるが、城門が閉まっていたため城内に逃げることができず、日本軍からうちだされる砲弾が作裂する中で死んだものである。
第四中隊は城内に入ったけれど、既に入っていた部隊の掃討が済んていたため敵兵は一人も見ることなく、数時間後にそのまま城外に戻った。
午後五時になると師団司令部が中華門から入り、市政府に司令部を置いた。(つづく)
次へ
戻る

 都城連隊の鎌田上等兵はほとんど眠ることもなく城壁上で十三日の朝を迎えた。寒かったけれど、緊張で眠気も空腹も感じない。城壁は占領したものの、城内の中国軍との戦いがひかえており、夜が明けると、他の中隊も破壊ロから登ってきた。新しく登ってきた兵隊は、揃うとそこから城内に下りて、町の中心に向かって進んでいった。
都城連隊の鎌田上等兵はほとんど眠ることもなく城壁上で十三日の朝を迎えた。寒かったけれど、緊張で眠気も空腹も感じない。城壁は占領したものの、城内の中国軍との戦いがひかえており、夜が明けると、他の中隊も破壊ロから登ってきた。新しく登ってきた兵隊は、揃うとそこから城内に下りて、町の中心に向かって進んでいった。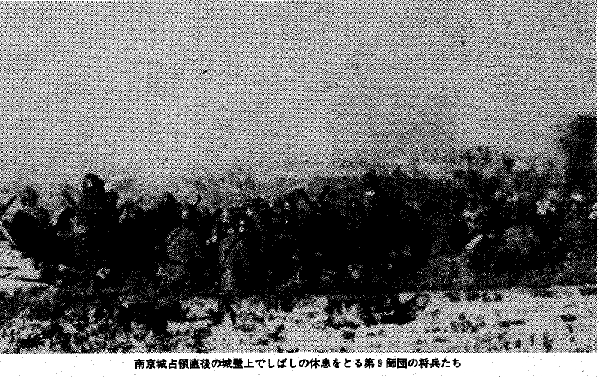 中山門から数百メートル進むと、明の故宮がある。南京城が建てられたのは明の太祖朱元璋がここを首都と定めた五百七十年ほど前で、そのとき、この地に宮殿が建てられた。即ち紫禁城で、八百メートル四方の豪華な宮殿である。しかし、その後、明の首都は北京に変わった上、清、中華民国と変わり、今はわずかに石の柱が残っているだけで、それだけから宮殿は想像もできなかった。あたり一面は野原で荒涼としている。しかも遺跡は中山東路で二つに分断されていた。
中山門から数百メートル進むと、明の故宮がある。南京城が建てられたのは明の太祖朱元璋がここを首都と定めた五百七十年ほど前で、そのとき、この地に宮殿が建てられた。即ち紫禁城で、八百メートル四方の豪華な宮殿である。しかし、その後、明の首都は北京に変わった上、清、中華民国と変わり、今はわずかに石の柱が残っているだけで、それだけから宮殿は想像もできなかった。あたり一面は野原で荒涼としている。しかも遺跡は中山東路で二つに分断されていた。 しかし、難民区では日本軍が恐れていることがおきていた。
しかし、難民区では日本軍が恐れていることがおきていた。