城壘11
丸MARU 1989年11月号 通算520号 連載第11回
″敵前逃亡″をはかる中国兵
南京城にある十九の門のうち、日本軍が最も早く攻撃を始めた光華門では中国軍も死に物狂いで守り、攻防戦は十二日で三日目に入った。門の外では鯖江連隊の第二大隊と第三大隊がいつ自分たちの出番が来るかと待っていたが、十二日午後二時になり、第二大隊に対して、第一大隊に代わって攻撃し光華門を占領するように命令か出された。
光華門の中の日本軍陣地を守っていた第一大隊では、第二中隊長の竹川中尉が竹川集成中隊として残っているすべての兵隊を指揮することになり、その竹川中隊を、新しく参加する第二大隊の檜皮少佐が併せて指揮することに決した。しかし、第二大隊もそのときは二百名足らずで、戦力としては中隊と殆ど変わらなかった。
ともあれ攻撃命令が出ると、第二大隊は早速光華門に補給を図った。しかしこの作戦はことごとく失敗した。
夕方になり重砲の砲撃が再開され、城壁の一部が崩れた。城門の外にはたそがれがせまってきた。第二大隊では夕闇を利用して城門内にいる兵隊に補給を図ろうとした。夕闇がさらに濃くなったころ、数十人か弾薬と食糧とともに城門に突入することになった。西坂上等兵もその一人に選ばれた。
間もなく突入の命令が下り、伊藤中隊長以下の突撃隊が光華門に向かった。
夕闇を利用した突入は成功した。
突入した数十人が光華門に入っでみると、城門の中はいたるところに日本兵の死体があった。生存者も傷つき、数日間は何も食べていなかったためほとんど生きる屍であった。しかも城壁上からは中国軍が休みなく攻撃をしてくる。西坂上等兵は、日本兵の死体の衝撃と頭の上から来る中国兵の攻撃で我を忘れた。ひたすら生存者の看護を続けた。
宇都宮の連隊は十二日の朝から南京城外の南にある雨花台を攻めていたが、まだ雨花台の半分以上は中国軍が確保していた。十一日の夜も砲声は一晩中頭上でうなり声をあげていて、夜も昼もなかった。高松伍長は既に二日もまともに食事をしていなかった。所持している食糧はなかったし、後方から補給されることもない。辺りの丘陵には塹壕の他にたまに畑があるので、運がよければ野菜が手に入ることがあり、それが食べ物であった。もちろん洗って食べるということはできないので、泥を落として生のままかじる。この野菜よりももっとまともな食べ物は中国兵の持っているものだった。中国兵は南京米を鍋で炊いて、そのときできたこげを雑嚢のようなものに入れていた。塹壕の中には多くの死んだ中国兵がいるので、死んでいる中国兵の持っている袋を探し出し、こげを見つけだすのだ。わずかなこげであったが、それが最も食べ物らしい食べ物て、見つければ、これを皆で分けて食べあった。
昼になると第四中隊が連隊の予備隊から第一線に出ることになった。高松伍長の所属している中隊である。しかしそれまで予備隊にいたといっても第一線とは数百メートルしか離れておらす、しかも中国軍の確保している塹壕と日本軍の占領した塹壕は入り乱れていたから第一線も後方も殆ど差はなかった。
第四中隊が第一線に立つことになったけれど、中国軍の撃つ迫撃砲が度々近くで破裂しているため中隊の統制はとれていなかった。そのためさしあたって小宅第一小隊長代理が高松伍長たちの第一小隊とさらに第三小隊を指揮して、城壁突入部隊を援護していた第三中隊の右翼に進むことになった。宇都宮連隊の中で最も右翼の位置である。
第四中隊が第三中隊の右翼に進むと、前方に鉄道線路とクリーク、そして城壁が見えた。城壁を前にしていた第三中隊は、宇都宮連隊の中では最も苦しい戦いを続けていた。中隊長以下悲槍な形相で、第四中隊は声をかけることもできなかった。
しかし、第百十四師団の中では第三中隊よりさらに苦しい戦いを続けている部隊がいた。第三中隊の左側で南京城を攻めている水戸の連隊である。
南京城の南側は第百十四師団と第六師団が攻めていた。第百十四師団の西を攻めた第六師団は、第百十四師団より早く城壁まで進んだため、第六師団の前にいた中国軍は第百十四師団の前方に移った。そのため、第百十四師団はもともと第百十四師団の前方にいた兵隊のほかに第六師団の前にいた兵隊とも対峙することになった。第百十四師団の中では水戸の連隊が最も第六師団よりを進んだため、水戸の連隊が多くの中国兵の攻撃を受けることになり、中華門近くまで攻めながらたびたび逆襲され後退するという戦いを続けでいた。だから水戸の連隊とくらべれば宇都宮の部隊は楽であった。
いよいよ高松伍長は最前線に進んで戦うことになった。最前線に立つと、敵の様子が分かるのは自分の両脇数十メートルと、その前方だけである。頭の上を中国軍の砲弾と日本軍の砲弾が飛び交っていて、中国軍が激しく抵抗していることだけがわかる。前線は膠着状態で、目の前に城壁が見えるが、城壁まで進むのにどのくらいかかるのか皆目見当かつかなかった。城壁前のクリークまではあと一キロメートルもなかったが、宇都宮連隊がここまでの三キロメートルを進むのに三日かかっている。
それでも前方にいる中国軍の様子はよく分かった。中国軍には督戦隊がいて、その督戦隊は、戦場で尻込みをしていたり、戦線から逃げようとする兵隊がいると、後ろから容赦なく射殺する。しかも督戦隊は精鋭の兵隊から編成されている上、強力な銃を持っているのて、狙われた兵隊は抵抗ができない。そのため、士気のない中国兵でも督戦隊が現れると死に物狂いで攻撃してくる。
その督戦隊を、南京城壁を前にして高松伍長は初めて見た。
中国軍は激しく日本軍と戦ってきたけれど、後ろはクリークや城壁て逃げ道がなかった。日本軍の攻撃はなかなかはかどらなかったけれど、それでもじりじりと攻めており、こ
のままでは最後に中国軍が全滅するのが目に見えていた。そのため中国軍の中には戦闘意欲をなくしている兵隊がいた。その兵隊を後方や城壁上から督戦隊が狙い撃つのだ。高松伍長が狙おうとしていると、突然督戦隊に撃たれて中国兵がたおれる。話には聞いていたけれど、非情な督戦隊に高松伍長はおどろいた。
そうやって少しずつ前進していった午後三時ころ、突然、前方にいる中国兵が白っぽい旗を振った。何かの合図なのか、それが何を意味しているのか高松伍長には分からない。日本軍からは攻撃が続いており、城壁上の中国軍からも日本軍を撃ってきている。白っぽい旗がまた振られたようだ。
降伏の合図なのかと一瞬思った高松伍長は、しばらくして撃つのをやめた。すると、数人の中国兵が高松伍長の方向に向かって歩いてきた。中国兵は日本側に逃けても助かるものなら助かりたいと思っているらしかった。すると城壁土の督戦隊がその兵隊たちをめがけて撃ってきた。督戦隊からみると彼らは敵前逃亡であり、射殺するだけである。高松伍長は、逃げてくる中国兵を見て督戦隊が狙うのは当然のような気がした。もちろん日本軍も逃げてくる中国兵めがけて撃ち続けている。日本兵にとっては、中国兵は南京城を死守するつもりで、降伏してきたとは思われず日本軍側に向かってきた中国兵は攻撃を続けていたのだ。それに、戦いの途中急に戦いをやめたといわれても、戦友を失っている日本兵の気持ちとしては戦いをやめるわけにはいかない。
高松伍長とは離れた先頭で指揮していた小宅小隊長代理も前方に白いものを見た。小宅小隊長は、白旗らしきものが見えると、その方向にむかって手招きをした。それを見た督戦隊は城壁上から小宅小隊長を狙ってきた。
しかし、最初の中国兵が日本側に逃げたと分かると、それに続く中国兵か現れてきた。 高松伍長に向かった中国兵はそのまま進んで、やがて高松伍長の前に現れた。
目の前に中国兵が現れた高松伍長は、戦いどころではなくなってきた。中国兵が立っているところは督戦隊から見えるところで、高松伍長も危なかったので、そのまま中国兵を後方に連れていった。
降伏してきた中国兵は、あちこちにおり、中国兵は自然と同じ場所に集められ、やがてその数は数百人にも達した。後方に連れてきて中国兵の攻撃から安全になるとはじめて高松伍長たちは落ち着いた。そこで中国兵の持っている武器を放棄させた。自動小銃、軽機関銃など日本兵より立派な銃を持っている者が多く、放棄させた重機関銃などで兵器の山がてきた。
武器は放棄させ、一安心はしたけれど、言葉が通じないので、混乱は続いていた。中国兵の中にはふてぶてしい顔をした者や、隙あらば飛び掛かってきそうな様子を見せている兵隊がいる。不安にかられた高松伍長は中国兵の巻脚絆をはずさせ、それで二人ずつ手を縛った。高松伍長だけでなく回りにいる日本兵も同じように思ったのか巻脚絆で縛りだした。巻脚絆といっても厚めの布であるからほどこうとすればすぐにほどけるもので、気休めにすぎなかったけれど、そうするより他に方法はなかった。 高松伍長はそれでも心配だったので、縛った中国兵を線路のそばに座らせた。
しばらくすると、雨花台の方に工場として使われていた建物があり、そこに中国兵を収容したらどうか、という話がおきたので、野外よりはと、そこに収容することにした。
引き続き高松伍長たちが中国兵を監視することになり、工場だったという建物まで中国兵を連れていくことになった。
夜になると、捕虜を監視していた高松伍長たちに食糧が届いた。高松伍長たちがまともな食事をすることができたのは三日ぶりである。日本兵たちはその一部を中国兵にも食べさせることにした。ところが驚いたことに、中国兵はどの兵隊も元気よくきれいさっぱりたいらげたのである。戦いの途中、簡単に逃げてくる中国兵にも驚いたけれど、日本軍に捕まってもこれほど食事がすんなり喉を通るのかと高松伍長はますます中国兵の気持ちが分からなくなった。
夜が更けるとともに建物の中はさらに騒がしくなりだした。督戦隊から逃れてくるときはおとなしい中国兵であったけれど、督戦隊から逃れろと、元の中国兵に戻り、そのため建物では監視の日本兵と一触即発の状態になった。中国兵の中には建物をゆさぶってあばれる者や、壊して逃亡をくわだてる者もいた。それを見た日本兵の中には、戦友をやったのはこいつらだ、と中国兵に斬りかかる兵もいた。城壁前の戦いが工場跡の建物の中で再開されたようなもので、建物は一晩中騒然としていた。
高松分隊たちは寝ないで中国兵の警備にあたることになった。しかし、二日にわたりまともに寝ていないので、誰もが体力の限界を越えていた。ときがたつにつれて、高松伍長は意識が朦朧となり、中国兵があばれたら大変だという気持ちがあつたけれど、こうなったらもうどうでもよいという気持ちの方が強くなっていた。
建物の回りにはまだ抵抗している中国兵がおり、日本兵と中国兵で混乱していた。特にクリークの前は中国兵と日本兵が右往左往して、言葉を交わさないと、敵か味方か全く分からなかった。
第百十四師団の中では、既に右翼隊となった高崎と松本の連隊が、東南にある雨花門から城内に入り、城門一帯を完全に占領していたけれど、水戸と宇都宮の左翼隊ぱとうとうこの日までに城壁を落とすことはできなかった。
光華門をめぐる攻防戦
 中山門外にある西山の山腹で一晩過ごした福知山連隊の山室分隊たちは、十二日の夜明けとともに頂上をめざして攻撃を始めた。
中山門外にある西山の山腹で一晩過ごした福知山連隊の山室分隊たちは、十二日の夜明けとともに頂上をめざして攻撃を始めた。
攻撃は順調に進み、第二中隊の援護もあって、正午過ぎには西山の頂上を占領することができた。
しかし、西山は南京城東側を守っている中国軍にとって城外最後の砦なので、午後になると兵をまとめて反撃をしてきた。しかも、死に物狂いの反撃て、近くにある紫金山や張学良の邸宅からも福知山連隊を狙って撃ってくる。
中国兵の反撃は強力で、山室分隊たちは占領した場所を確保するために、再び陣地を築かざるをえなかった。今日こそ西山を占領した上に中山門を攻撃しようと思っていたけれど、確保するのが精一杯で、そのためこの日も西山にとどまることになった。
それでもこの日、山室分隊には久しぶりに乾麺包半袋と味噌、缶詰の配給があった。ここ一週間ほど前線では毎日一キロかニキロしか前進することかできなかったので。遅い輜重部隊も追いついたのである。
この夜も一晩中中国軍の砲撃が続き、砲声がやむことはなかった。特に迫撃砲はたびたび近くに落下し、真夜中には十メートルほど近くに落下した迫撃砲て山室分隊全員が頭から土をかぶった。
夜になって横になると、山室伍長も疲れを感じた。しかし、こうやって怪我もなく日本のため天皇陛下のため戦ってこれたことに感謝せすにはいられなかった。自分を守ってくれたのは神様か、自然の力なのか、鎮守の森なのか、あるいは親なのか、とそれぞれにおもいを巡らした。そして、それらすべてが自分を守ってくれていると思うと心が生き生きとしてきた。生死の境におかれていたため、いつもと違って感謝の気持ちでいっぱいになっている自分に驚きもした。
揚子江右岸を進んでいた仙台と会津若松の部隊のうち、仙台の部隊だけは十二日炭渚鎮に来たとき、揚子江を渡ることになった。先に揚子江を渡った部隊と一緒になり、南京の背後に向かうためである。残った部隊は山田栴二旅団長以下、会津若松第六十五連隊、山砲一大隊、騎兵一大隊になつた。
午後になりこの部隊に、南京の揚子江沿いにある烏龍山と幕府山を攻めるように命令が下った。
烏龍山と幕府山は南京城と揚子江の間にあり、この山にも揚子江に向けた砲台がある。揚子江岸最大の要塞があった江陰を無事通過した海軍の砲艦は、その後揚子江左岸から撃ってくる敵と交戦しながら、この日の午後には烏龍山下流にある閉塞線まて到達していた。
また、烏龍山の砲台は揚子江だけに向けられているのではなく、内陸にも向けられている。その砲台が紫金山の北側から南京に向かった奈良の連隊をも砲撃していた。揚子江沿いに攻めていた会津若松第六十五連隊にこの砲台攻撃命令が出されたのは当然である。
しかし、鳥龍山は炭渚鎮から二十キロメートルも先である。このため部隊は命令が出るとただちに出発し、十二日の深夜に烏龍山のふもとまで進んだ。
西南の城壁上にいた中国兵は、十二日午後、いったん城壁上を水西門のほうに退却したが、砲撃がやみ、夕闇がせまると態勢を立て直して攻めてきた。喚声をあげて城壁上を走りながら進む姿は、遠くの城壁上にいた大分連隊の兵隊にも見えた。
大分の連隊は竹梯子で登ったため、城壁上を占領したのはわずかな兵隊で、中国軍の本格的な反撃があったらもちこたえられるかどうか危ういところであった。そういうときに城壁上を中国軍の兵隊が進んできたのである。
大分の兵隊よりさらに水西門側にいた都城の鎌田上等兵たちは土嚢を掩体にして、進んでくる中国兵を待ちうけた。
このとき、すでに野重砲の観測兵たちは第九中隊と踵を接するように城壁上に登ってきていた。そのため城壁上を攻めてくる中国兵に対してまず野重砲が砲撃した。
都城連隊の中でも、まだ第九中隊しか城壁にたどりつくことができない状況の中で、野重砲の観測兵たちが城壁上まで観測地点を進めたことは勇敢なことで、こうして中国兵は撃退され、都城の部隊も大分の部隊も無事だった。野重砲の活躍には後に第六師団長から賞詞が授与された。
城壁上を攻めてくる中国軍は野重砲に撃退されたけれど、南京城内からは破壊ロの日本兵をめがけて砲撃が続いていた。中華門を目標にしていた熊本の連隊はまだ中華門に達していなかった。また、大分の連隊では城壁上まで登った兵隊はごくわずかであった。そのため南西の破壊ロにいる都城の部隊だけが中国軍の標的であった。
これに対して日本の野重砲も中国軍の砲台のある清涼山を砲撃し、夜の十時半ごろまで砲撃は続いた。
城壁上を攻めてきた中国兵は撃退されたけれど、完全に夜のとばりがおりると中国軍の攻撃が再開された。牛島旅団長は避難しようともせす、第九中隊を督戦する。何度目かの夜襲のとき、中隊長はむりやり牛島旅団長に城壁上のトーチカに避難してもらった。
夜が更けるとともに夜襲は小規模に、そして間遠になってきた。
鎌田上等兵は城壁上で中国兵の攻撃にそなえているうちは夢中だったが、中国軍の攻撃か一段落すると急に寒さを感じてきた。クリークに落ちたとき軍服がびしょぬれになっていたからである。そこで城壁の上で死んでいる中国兵の服をはぎ取って羽織った。
中国軍の攻撃は小規模になったけれど、真夜中まで続いていた。
城壁上にひるがえる日の丸
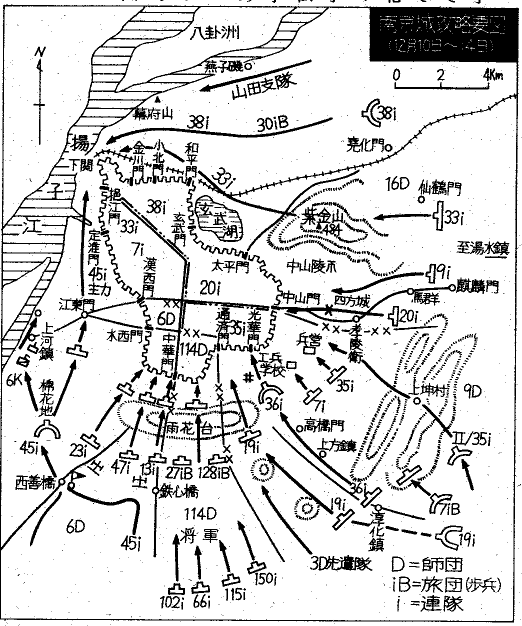 十二月十二日の昼すぎに、大分の第四十七連隊が城壁上まで登った。夕方には都城第二十三連隊が西南角の城壁を破壊し、城壁上を占領した。また、第百十四師団の高崎と松本の部隊も夕方には東南角の鉄道出入り口から城内に入りつつあった。日本軍が最初に城門攻撃をした光華門では攻防が三日目に入っていた。
十二月十二日の昼すぎに、大分の第四十七連隊が城壁上まで登った。夕方には都城第二十三連隊が西南角の城壁を破壊し、城壁上を占領した。また、第百十四師団の高崎と松本の部隊も夕方には東南角の鉄道出入り口から城内に入りつつあった。日本軍が最初に城門攻撃をした光華門では攻防が三日目に入っていた。
このため唐生智南京衛戌軍司令長官は、南京城防衛もこれまでと観念し、南京からの脱出を決意した。自らは挹江門方面から脱出するとともに、南京防衛にあたっていた全軍に、日本軍の包囲を突破して南京を脱出するように命令した。
この命令は一斉に各門に伝わり、十二月十二日午後十一時を期して総退却が行われることになった。
夜中になり各門の守備についていた中国兵は命令通り日本軍を攻撃しつつ撤退を始めた。
十二月十三日の午前一時になり光華門の鯖江第三十六連隊ではあらたに連隊長命令が発せられた。午前八時、夜明けとともに光華門総攻撃を行うという命令であった。八時から十時までの二時間、重砲により城壁を攻撃して瓦礫による斜面をつくり、一方、山砲などによる城門への砲撃を行い、十時とともに檜皮少佐以下第二大隊が一斉に城門に突入するというものである。
既に光華門に突入していた西坂上等兵は光華門内の土嚢と瓦礫の中で夜が明けるのを待った。回りは真っ暗でだれがだれか分からない。門の中は日本兵の死体がごろごろして死臭、異臭がみなぎっていた。あと数時間でいよいよ最後の攻撃である。中国軍の抵抗が強ければ第二大隊にも第一大隊と同じ運命が待っている。鯖江を出発するとき、脇坂連隊長が、「みんなの命は連隊長がもらった」と訓示したことが思いだされた。上海でも、淳化鎮でも、何度か危ういときがあったけれど、いよいよそのときが自分にもきたのかと思った。
西坂上等兵はまんじりともせす光華門の中で夜の明けるのを待っていたが、刻々と緊張の度が高まるにつれて、城門上は反比例して静かになってきた。嵐の前の静けさというのであろうか。
しばらくして、伊藤中隊長が、「指揮班長、ようすを見てこい」と命令した。指揮班にいた西坂上等兵は指揮班長に従って城門内の瓦礫を登った。
途中から城門の煉瓦に足をかけて城門の上まで登って、そろそろと頭を出した。中国兵が待ちうけていれば、一発で殺される。中国兵にわからないように、しかも城壁上が見えるまで頭を出さなければならない。
ぎりぎりまで頭を出すと、中国兵の動く影は見えない。薄気味悪いほど静かで、どこからも手榴弾はとんでこない。そこでさらに頭を出して見たが、城壁上には一人の中国兵も見えなかった。
既に中国軍は全員撤退していたのだ。連隊長命令が出て、いよいよ、と決死の覚悟でいただけに西坂上等兵は拍子抜けしてしまった。二人はすぐに瓦礫を降りて中隊長に報告をした。
中国軍が撤退したという報告に第二大隊はただちに城門の外に出た。そして城門左の崩れた城壁から登った。竹川集成中隊は右側の崩れた城壁から登った。やはり中国兵の抵抗はなかった。
城壁上に登り、鯖江連隊は完全に光華門を占領した。まだ回りは真っ暗で、時刻は四時過ぎであった。
午前五時になると、土手下の工兵学校にいた連隊本部も軍旗を奉じて光華門に登ってきた。連隊本部が城壁上まで登ってきたとき、鯖江連隊は始めて皇居を遥拝し、万歳を三唱した。兵隊たちは持っていた日の丸の旗をそれぞれ城壁上に立てた。立てられた何本かの日の丸の旗は光華門の上ではためいた。
やがて十三日の朝が白々と明け始めてきた。西坂上等兵は光華門の城壁の上に立って南京城内をながめた。城内の何カ所かからは黒煙が立ちのぼり、天に冲していた。いつものように中国軍が退却するにあたって放火した煙であるらしかった。城内からは何ひとつ音が聞こえてこず、静かである。
城門内にいるとき、西坂上等兵は、中国兵がどこから撃ってくるかわからなかったから常に防衛の姿勢をとっていた。瓦礫の中で十時間もの間小さくなっていたがもうその必要はない。城壁上では思い切って背伸びをした。何度も何度も背伸びをした。
そこへ同じ中隊にいた従兄弟の高橋太重郎伍長がやってきた。従兄弟は、西坂上等兵を見ると、「元気で運の強い男だな」と言った。半分あきれているような言い方だった。
従兄弟にそういわれたけれど。西坂上等兵は何故かむやみに嬉しかった。ついに南京城を攻略したのだ。嬉しくて仕方がなかったのだ。
連隊長命令ては、城壁を占領した後、引き続き城内の敵を攻撃することになっていたが、光華門上から見るかぎり城内には敵は見えなかった。中国兵の死体もほとんどなかった。中国軍は引き上げるとき、中国兵の死体をも運んだのであろう。
しかし城内は城外と違って建物が密集しているから中国軍は建物の中に隠れているのかも知れない。上海では中国兵は建物に拠って戦ったからありうることである。もしそうなれは城壁攻略よりめんどうな戦いになるかもしれない。西坂上等兵は門の上でそう思った。(つづく)
次へ
戻る

 中山門外にある西山の山腹で一晩過ごした福知山連隊の山室分隊たちは、十二日の夜明けとともに頂上をめざして攻撃を始めた。
中山門外にある西山の山腹で一晩過ごした福知山連隊の山室分隊たちは、十二日の夜明けとともに頂上をめざして攻撃を始めた。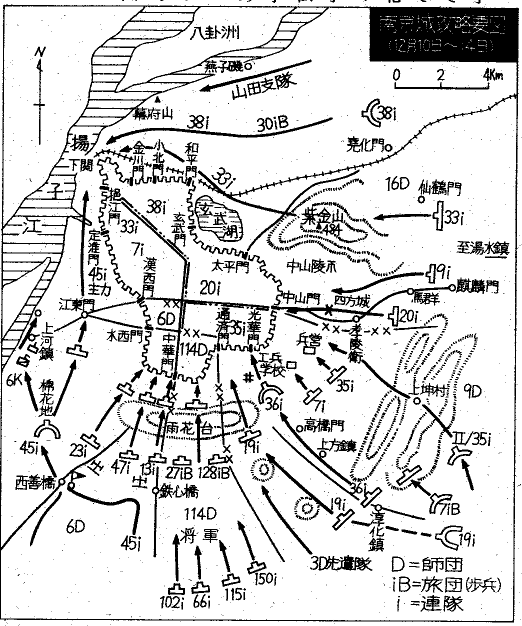 十二月十二日の昼すぎに、大分の第四十七連隊が城壁上まで登った。夕方には都城第二十三連隊が西南角の城壁を破壊し、城壁上を占領した。また、第百十四師団の高崎と松本の部隊も夕方には東南角の鉄道出入り口から城内に入りつつあった。日本軍が最初に城門攻撃をした光華門では攻防が三日目に入っていた。
十二月十二日の昼すぎに、大分の第四十七連隊が城壁上まで登った。夕方には都城第二十三連隊が西南角の城壁を破壊し、城壁上を占領した。また、第百十四師団の高崎と松本の部隊も夕方には東南角の鉄道出入り口から城内に入りつつあった。日本軍が最初に城門攻撃をした光華門では攻防が三日目に入っていた。