城壘06
丸MARU 1989年6月号 通算515号 連載第6回
徴発という名の略取
南京攻略が決まった十二月一日、この日も上海から南京にかけては天気の良い日であった。このとき南京には七つの師団の部隊が向かっており、最後に上海戦に参加した第十六師団は常州から丹陽に向かおうとしていた。
第十六師団は師団司令部が京都にあり、京都、福知山、津、奈良の連隊で編成されている。北支の戦火が広がって、一ヵ月ほどした八月には天津に派遣されたけれど、戦いの中心が上海に移ったためつい二週間前、大連から船に乗って揚子江河ロの白茆口や滸浦鎮に上陸したばかりであった。
上陸した滸浦鎮一帯は、南船北馬といわれている通り、クリークが縦横に走っている。北支では黄色っぽい土地がどこまでも続くだけであったので、十六師団の兵隊はだれもがその違いにとまどった。
常州まで進んだとき鯖江の部隊と一緒になったけれど、常州を出発するときには別れ、鯖江の連隊は丘陵地帯を西に進み、第十六師団は運河に沿って北西の丹陽をめざして進むことになった。
丹陽に向かう幹線は運河である。運河の他に鉄道と自動車道路も走っているけれど、昔からの運河がいまも交通の中心となっていた。この運河は大運河とも呼ばれ、隋の時代に煬帝が造ったもので、すでに千三百年もの間、主要な交通路として使われていた。運河が造られるときには苛酷な作業のため何百万人も死んだといわれ、工事の規模では北にある万里の長城と並び称されているものである。
ふつうならば舟で運河を進むのであるが、いたるところにいる中国軍と戦いながら進まなくてはならないので、第十六師団は舟を曳くために運河に沿って走っている道路を進んだ。
この日、第十六師団の四つの連隊のうち、福知山の部隊が先頭になり、福知山連隊のうちでも、第三大隊が前衛をつとめていた。
このため後衛にいた第一大隊の山室分隊は昨日と同じように一日中歩くだけであった。時折、部隊の上を日本の飛行機が丹陽に向かって飛んで行くのが見えた。
山室分隊たちは、夜九時ごろ呂城鎮を通過したが、まだ休みという声はかからなかった。ここでは昼に戦闘があったらしく、あちらこちらに日本軍と中国軍の戦った跡が残っていた。夜十時に大王廟付近の小さな部落に着いたとき、命令が来て、ようやく今日はここに宿営することになった。
命令と同時に兵隊たちは食事の用意に入った。部落での宿営なので、さっそく民家に入って食べ物を探しはじめた。徴発である。
ほとんどの中国人は逃げるときに食べ物を隠して行く。徴発といってもそれを探すのであるけれど、いくら中国人が上手に隠しても必ず見つけだした。探す方が隠す方よりはるかに真剣だからである。
山室部隊の分隊長である山室正三伍長は毎日探しているうちに、中国人がどういう場所に隠すかわかるようになってきた。
中国人は食べ物をほとんど家の外に隠す。日本兵の意表をついたつもりなのだろうが、どこの家でもそうなので日本兵にとっては意表をついたことにならなかった。
しかむ隠し方が不自然なのですぐにわかる。中国人が隠す主な方法は地中に埋めるという方法であるが、埋めた後、その上に草で×の印をつけておいたり、棒を立てておいたりする。また、草を積み上げて隠すこともある。だから不自然に盛り上がっている草があってどけてみると、ほとんどといってよいほど食べ物が現れた。どれもが一見してすぐわかるほどで、見つけるたびに、中国人は自分で隠した場所を忘れてしまうからなのだろうかと不思議に思った。
もちろん、いつも見つけることができるわけではなく、何も見つけだせないこともたびたびあった。そんな時は、見つけだせないのではなく、何も隠されていないのだと思っていた。
間もなく一人の兵隊が小豆をみつけてきた。いつも徴発してくるものは、南京米、甘薯、漬け物などと決まっているが、小豆ははじめてなので、山室分隊の兵隊たちは大喜びした。さっそく煮ておかずにすることにしたが、それでもまだ余ったので、その分は南京米と一緒に煮ることにした。
小豆は料理前にしばらく水につけておかなくてはならないが、少しでも早く食べたいし、食べたらすぐに寝なくてはならない。悠長なことはしておれないので、水につけることもなく飯食炊さんにかかった。山室分隊は予備隊として後方にいるので、飯倉炊さんの火に気をつける心配もなかった。いつものように明日の朝と昼の分とあわせて三回分を炊いた。小豆飯というので、兵隊の一日の疲れはふっとんだ。
食事が終わると、それぞれ藁などを探してきて寝る用意をはじめた。戦場での最大の楽しみは食べることで、その次が寝ることである。食べる時と寝る時が一度にやって来るこの時間は、一日のうち最も楽しいときであった。
藁も何もみつけだせなかった者はそのまま寝た。戦場では師団長であろうが、旅団長であろうが、藁が最上の布団であった。すでに十二月に入っていたが、二十歳そこそこの兵隊は風邪もひかない。戦場というので寝ていても緊張しているせいかもしれなかった。
六時間ほど寝て、十二月二日は暗いうちに起こされた。
この日は山室分隊の属している第一大隊が先頭に立つことになった。先月末は無錫で三日間休み、さらにその後三日間は後方を進んだので、第一線に立ったのは七日ぶりであった。
分隊長の嘆願書
まだ真っ暗な六時に、第一大隊は大運河に沿って丹陽に向かった。
七時を過ぎると、ようやく明るくなりはじめる。まわりは麦畑で、ところどころ桑畑もある。揚子江岸に上陸して以来の同じような風景だ。
昼近くになり、先を進んでいる尖兵が敵と遭遇したらしく、前方から撃ち合う音が聞こえてきた。あたりいちめん平坦な地で、遥か向こうには丹陽の町らしい建物と林が見えてきた。
丹陽は唐の昔からの町で、大運河の要路として栄えてきた町である。絹織物の産地でもある。南京から百キロも離れているが、上海から南京に向かう平坦コースにあたっていたから、ここには南京防衛の防御線が築かれていた。すでに相当の中国軍がここで日本軍を待ち受けているらしかった。
近づくにつれて林の向こうには、古びた高い塔がはっきり見えてくる。日本軍は遮蔽物は何もない所を進んでいるので、中国側からは日本軍が手にとるように分かるようであった。迫撃砲が林の向こうから激しく撃たれることからそれが想像できた。
午後になり丹陽の陣地直前まで進んだ福知山連隊は、いよいよ連隊砲で中国陣地めがけて砲撃をはじめた。その後、重機関銃隊の射撃がはじまった。
重機関銃隊の分隊長である山室伍長は、いつものように重機関銃の前に立った。目標を指示し、効果を確認するためであるが、分隊長が立つ場所は中国側から最も目標となりやすく、それだけ日本軍の中では最も危険な最先端である。そのためこの場所は銃側即墓場といわれていた。
日本の兵隊の中では東北や九州の兵隊が素直で我慢強く、日本陸軍の中でも特に精鋭な兵隊といわれていた。都城の連隊がその代表である。一方、東京や大阪の兵隊は軟弱で都会ずれしており、東北や九州の兵隊と比べ格段に落ちるといわれていた。京都の第十六師団もそんな弱い部隊の一つといわれていた。
しかし、山室伍長は自分を勇気のない、弱い兵隊と思ったことはなかった。
山室正三は丹波で何代も続いた旧家に生まれた。父は村長で、生家は村一番の大きい家であった。家の隣は村の集会所で、さらにその隣には鎮守の森がうっそうと茂っていた。山室家は村の中心にあり、この東八田村全体が山室家を中心に動いていた。
そういう家に四人兄弟の末っ子として生まれ、色の白い小さい子供ではあったけれど、小さいときから元気があった。
二十歳になった三年前、徴兵で軍隊に入ったときも、子供のころの元気な性質は変わらず、特別に兵隊が好きだったわけではなかったけれど、兵舎の中では立派な兵隊として認められた。
入隊して間もなく、山室一等兵も満州に行った。満州に行ったときも、命が惜しいとか、戦争が怖いなどと考えたことはなかった。
満州から戻ってしばらくして満期除隊したけれど、除隊したときのことを考えてもいなかったので再び学校に通いだした。
除隊して一年ほどした頃、蘆溝橋事件がおき、山室正三は再び召集された。
今度の事変は、満州とは違っていた。相手は満州の匪賊ではなく、中国の正規軍である。しかも、中国は日ごとに反日になって、日本は長年築いた国益をおびやかされている。国民はだれもがそう思って心配して、この戦いに日本軍は必ず勝たねばならないと思っていた。
そういうところへ召集されたから、山室正三は召集されたことを喜び、自分が行って必ず中国軍に勝ってみせると心に誓った。
召集され、福知山連隊に行くと、連隊はあわただしく出陣の準備をしている最中で、その兵隊たちはすぐに北支に向かって行ってしまった。山室伍長たち一部の兵隊は留守部隊として兵舎に残された。
喜んで入営しただけに、自分だけが残されたことにがっかりし、多くの市民に見送られていった兵隊をうらやましく思った。
山室正三が留守部隊に残されたのは、現役時代の上官がたまたま留守部隊にいて、かわいがられていたため残されたのであったけれど、それが山室正三には不満であった。
やがて中国に行った部隊から戦死者、戦傷者の知らせが留守部隊に入ってきた。そんな知らせを聞くたびに早く戦場に行きたい気持がつのった。
然し、戦死傷者が多くなれば留守部隊から補充部隊が編成されるはずである。
山室正三は補充部隊が編成されたら、まず一番に選んでもらおうと思った。選んでもらうには自分の気持ちを前もって知ってもらわなければならない。そのため仲間二人と嘆願書を書くことを思いたった。
仲間の二人は山室正三より二つほど年上で、同じように召集されて留守部隊に残され、残されたことを憤慨していた。自分たちの気持ちを知ってもらうためには血の嘆願書を書くことであった。
嘆願書を書こうとした時、特別の気負いもなく左手の小指を剃刀で切った。戦場に行きたいという気持ちだけが強く、半分ほど切ったけれど痛いとは感じなかった。小指をしぼるようにして血を
出し、右の人差し指につけて、早く戦場に行かしてくれるように、と書き、最後に自分の名案を書いた。
血の嘆願書を書いたのは山室伍長ら三人だけではなかった。留守部隊には同じように、血の嘆願書を書いたり、血判を押すものが何人もいた。
血の嘆願書のせいか、十月に六十三人の第一次重機関銃補充隊が編成されたとき、山室伍長はその一人に選ばれた。
すぐに北支に向かい、部隊に追いついて第一大隊の第一機関銃中隊第四小隊の第七分隊長を命ぜられた。
そんな兵隊だったからきわめて勇敢な下士官だった。まわりでどんなに激しく敵の銃声、砲声がひびこうが気にならなかった。自分では戦争は命がけのスポーツのようなものだと思っていた。
突然の追撃命令
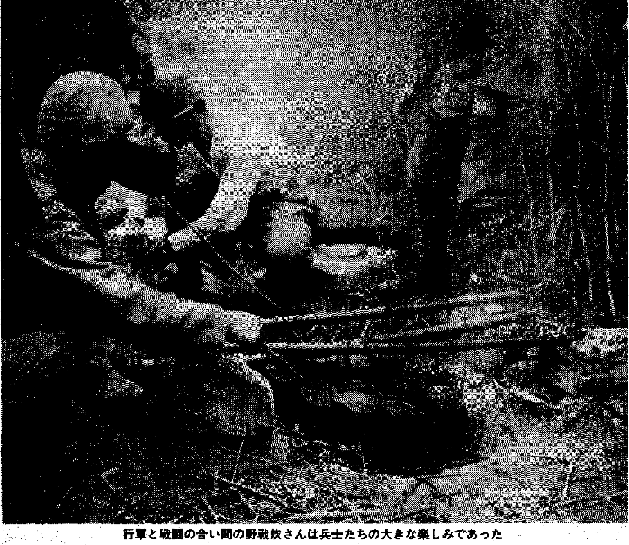 丹陽の敵陣地は町の前方一キロほどの所にあったが、重機関銃の猛射のあと、各中隊はトーチカに突撃し、重機関銃隊もすぐにそれに続いた。
丹陽の敵陣地は町の前方一キロほどの所にあったが、重機関銃の猛射のあと、各中隊はトーチカに突撃し、重機関銃隊もすぐにそれに続いた。
五時半ごろには町の前方にある陣地を占領し、その後も町の中心に向かって攻撃を続けた。大運河から流れる濠が丹陽城を囲んでいて、町の中心部はその城の中にある。攻撃を続けながら夜八時には城の一角まで進み、最後の攻防になった。
それから数時間、中国軍は抵抗したけれど、夜の十一時ごろになり、ついに丹陽城から敗退していった。
すでに真夜中だったので、連隊はその場所で夜を明かすことになった。山室分隊は奪った敵の陣地で寝ることにした。
壕の中で数時間寝たと思ったら四時には起こされた。中国兵は丹陽城から一人残らず逃げたようであったが、改めて掃討しなくてはならないというのだ。山室分隊は明るくなりはじめるころに、濠にかかる橋から城内に入った。
城内に入ってみると。二万はどの市民はほとんど避難していなかった。町は逃亡のさいの混乱と、日本軍の砲撃で荒れて、日本軍の飛行機による爆撃の跡もあった。いたるところに「打倒日本帝国主義」「契不売買日貨」といったスローガンの書かれている紙が貼られていた。
それを見て、中支の中国人は北支と全く違うと感じた。北支ではまったく見られない光景であった。南では蒋介石の威令か行き渡り、反日の教育が徹底していると聞いていたが、考えていた以上のものであった。北と違うのは風景だけではない。気を引きしめなければならないと思った。
午後二時には丹陽を出発し追撃に移った。丹陽城内にめぼしいものは何も残っておらず、中国兵が略奪していったのは明らかだった。その証拠に中国兵は持てるだけ持って逃げるが、間もなく持ち切れなくなると捨ててしまう。追撃戦になると、そういうものが必ず道路に捨ててあった。今日もそうであった。最初に捨てるのが毛布、水筒、靴、帽子などで、なかには魔法壜なども捨ててあった。
その後に捨ててあるとしたら、こうもり傘である。中国兵は雨が嫌いで必ずこうもり傘を持って逃げるというが、疲れるとこうもり傘も捨てる。何を持ちすぎたのか、弾、軽機関銃、手榴弾などが落ちていることもめずらしくなかった。
最後まで持っているのが食べ物で、南京米、缶詰、餅、菓子などである。食べ物はすべて日本軍が利用したけれど、菓子といっても中国の菓子は甘くないものが多かった。山室伍長はもともと甘党だったので、菓子というと喜んで拾ったけれど、いつもがっかりさせられた。
丹陽を離れるにしたがいクリークは少なくなる。夕方六時には丹陽から二十キロほどの白兎鎮に着いた。白兎鎮は小さな部落で、ここも城壁で囲まれていた。
南京攻略の命令は昨夜上海派遣軍から各師団に出されていたが、第十六師団では、遅れている弾や食糧が来るのを待って、準備をととのえてから攻略に移ることに決まった。津や奈良の部隊はまだ丹陽にいる。そこで先頭を行く福知山の部隊は白兎鎮に留まり、上からの命令を待つことにした。
そんな上の方針はすぐに伝わってくる。途中さまざまな推測が入り、兵隊たちにはそのまま伝わることはないが、誰がいうということもなく一週間くらいはここにとどまりそうだとなった。
福知山の連隊は白兎鎮でとりあえず休養をとることになったため、山室分隊では四日朝早くから徴発に出かけた。
朝方、徽発に出かけた兵隊たちが戻ってきたのは夕方であった。豚、鶏、南京米、甘薯などいろいろなものを徴発してきた。たちまち分隊は大騒ぎになった。
ところが昨日まで食べるだけで満足していた兵隊も、今日のように徴発品がたくさんあるとかえって不満が出てくる。久し振りに肉を食べられるというのに一人の兵が野菜も食べたいと言い出した。一人がそう言い出すと、しばらく食べていないので誰もが急に野菜を食べたくなった。人間のぜいたくはきりがないものである。食べることだけが兵隊たちの唯一のぜいたくであったから仕方がないのかもしれない。
野菜もたまには徴発できるが、この辺りには、日本にあるような大根はなかった。
山室伍長は大根が特に好きだったのて野菜の話になると高槻大根を思い出した。丹波の近くにある高槻という部落でとれるおいしい大根である。
同じ丹波生まれの兵隊が、山室伍長の大根好きを知っていて、「高槻の大根を食べたいなあ」と言った。丹波では高槻大根が有名だったから、それを聞いてすぐにあいづちを打つ者がいた。高槻大根の名前を聞くと、山室正三は目の前にあるごちそうを食べなくとも大根だけは食べたいと思った。ないものだけにむやみとほしくなる。
不満は食べ物だけに限らなかった。近くにあるクリークの水が濁っていると一人の兵隊か言い出した。きのうまでは浮いている死体を押しやって水を汲み、それで飯を炊いていた。そうやっても平気だったのに、今日は四キロほど先に水のきれいな部落があると聞いてわざわざそこまで行くことになった。
そんなことをやってしばらくのんびりしていると、突然、夜九時になって、句容の敵が退却したので追撃、という命令が来た。一週間ものんぴりできると思っていた兵隊たちはあわてた。
句容は二十キロ先で中国軍の陣地があるところだ。いよいよ第十六師団も本格的に南京攻略に向かうことになったのだ。
句容への攻撃には、福知山連隊の他に、同じ第十六師団の京都の連隊も向かうことになり、夜中の行軍が始まった。
山室分隊は真夜中の三時に句容郊外に着いた。
句容への攻撃は五日の早朝から始まった。句容も町の中心は城内にあったので、ここへ攻撃が集中された。
飛行場もあり、丹陽より防御は堅かったけれど、日本軍は昼までに城内に攻め入り、占領した。句容もそうであったが、日本軍は戦えば必ず勝った。
山室分隊は城内に入らず、郊外にとどまったままで、その夜は郊外に宿営した。
この日の夜中から句容は冷え込み、翌六日は零下五度という寒い日になった。句容だけでなく、太湖から南京一帯が寒気におおわれ、あちらこちらに氷がはった。山室分隊たち第一大隊は午前六時に宿営地を出発し、句容城には入らず、そのまま句容から北西十二キロにある湯水鎮に向かうことになった。(つづく)
次へ
戻る

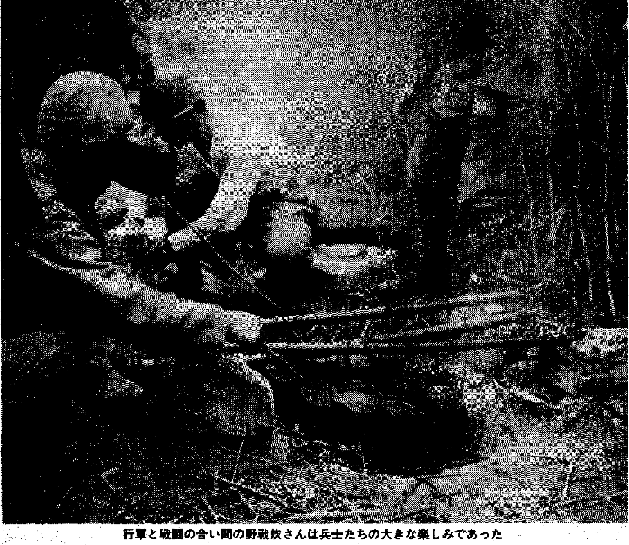 丹陽の敵陣地は町の前方一キロほどの所にあったが、重機関銃の猛射のあと、各中隊はトーチカに突撃し、重機関銃隊もすぐにそれに続いた。
丹陽の敵陣地は町の前方一キロほどの所にあったが、重機関銃の猛射のあと、各中隊はトーチカに突撃し、重機関銃隊もすぐにそれに続いた。